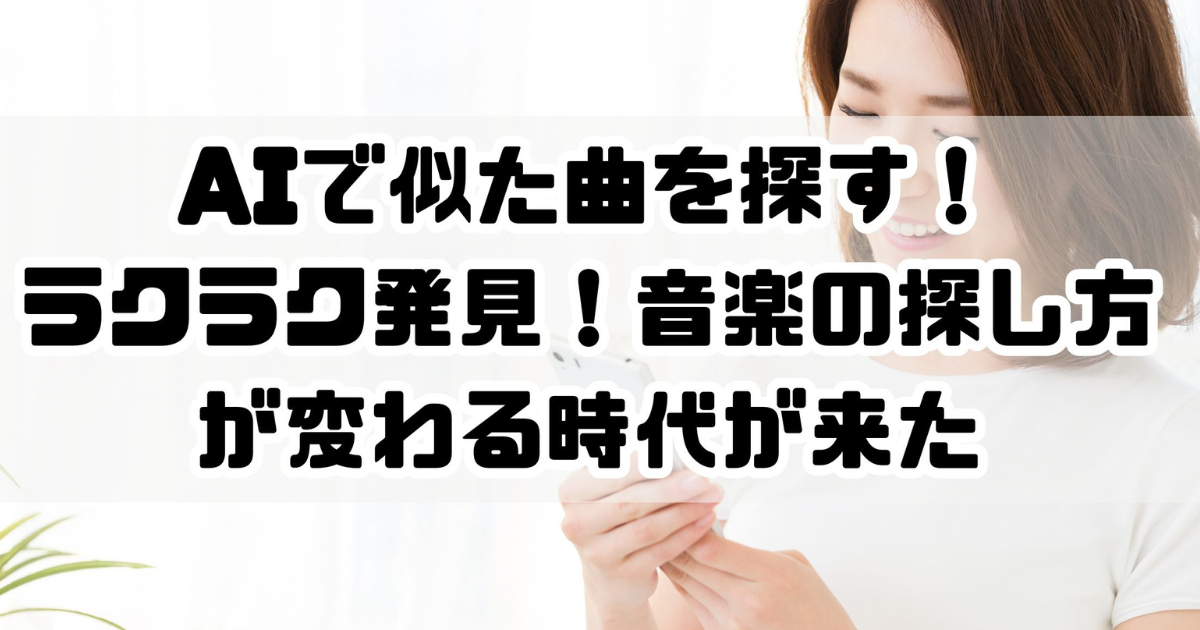
AIの力で「この曲なんだっけ?」を秒速解決!似た曲を指すときの方法
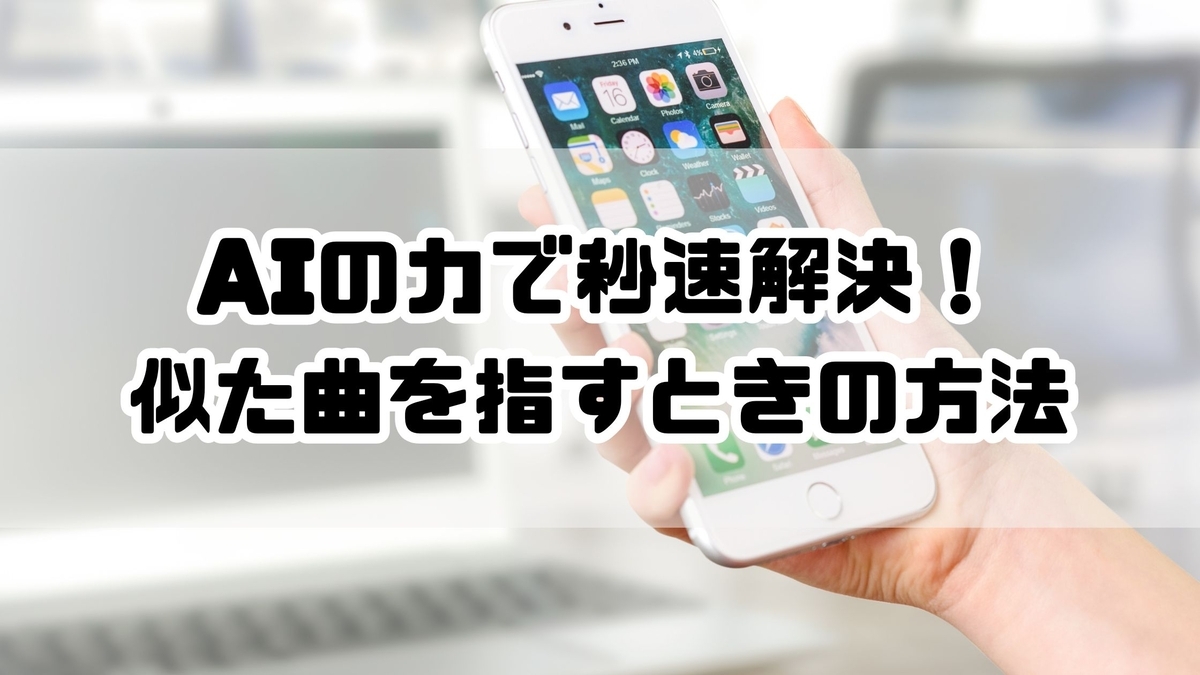
最近のAIって、ほんとスゴイですよね。 画像を自動で生成したり、動画編集をアシストしてくれたり、日常のあちこちで活躍中。 そんな中、音楽の世界でもAIが大活躍しているってご存じでしたか?
特に注目したいのが、「音楽検索AI」なるジャンル。 街中やカフェでふと流れてきた曲、思わず「この曲、誰のなんて曲?」ってなる瞬間、ありますよね。
そんなときに救世主となるのが、音声認識や機械学習を活用したAIツールたち。 今回はその代表格ともいえる『Shazam(シャザム)』をご紹介します!
Shazamって何?どうやって使うの?
Shazamは、音楽を数秒聞かせるだけで、曲名やアーティストを即座に教えてくれるスマホアプリ。
「え、そんな簡単にわかるの!?」って思うかもしれませんが、ほんとに簡単。 たとえば、YouTubeを見てて気になるBGMが流れたときや、レストランで流れてる音楽が「いいな」と思ったとき、 スマホに向かってShazamを起動してポチッとするだけ。 数秒後には「この曲ですよ〜!」と教えてくれるんです。
どうやって曲を判別してるのかというと、Shazamは「音楽の指紋」と呼ばれるその曲特有のデジタル情報を取り出します。
たとえば、街中でふと耳にしたメロディーが気になったとき、その曲を一瞬で探し出してくれる便利な仕組みがあります。この仕組みは、例えるなら「音の指紋」を手がかりに探偵が犯人を突き止めるようなもので、膨大な音楽のコレクションと照らし合わせながら、ぴたりと一致する曲を見つけてくれるんです。
その裏には、実はとても高度な技術が詰まっています。機械学習という、自分でどんどん賢くなるコンピューターの力と、人の声や音を聞き分ける音声認識の技術。この2つが合わさることで、なんと100万曲以上ものデータの中から、ぴったりの一曲を瞬時に見つけ出せるようになっているんですね。
こうして書きながら、「機械が音を覚えて、似ているものを探すなんて…ちょっとした耳のいい友達みたいで面白いなぁ」と思ってしまいました。
Shazamを起動するだけ。 誰でも一瞬で使いこなせちゃう優れモノなんです。
実際に使ってみた感想(正直レビュー)
筆者も実際に使ってみましたが、メジャーなアーティストの曲にはめちゃくちゃ強い! 「え、こんなマニアックな洋楽も分かるの?」ってくらい認識力が高いです。
ただし……
ちょっと気になったのが、フリーBGMやマイナーなインディーズ曲にはやや弱い印象があるところ。 というのも、Shazamのデータベースは主に商業音楽が中心なので、 あまり知名度のない曲や個人制作の音楽などは、そもそも登録されていないケースが多いんです。
なので、カフェで流れてたおしゃれなBGMを調べようとして「該当なし」と出たときは、 「そっちの曲は聞き取れんのかーい!」とツッコミたくなることも(笑)
とはいえ、メジャーな楽曲に関してはかなりの認識精度なので、 普段の生活で「あの曲なんだったっけ?」と思う場面では、まさに心強い相棒になってくれます。
音楽好きな方はもちろん、たまに気になる曲に出会う人でも、 Shazamをスマホに入れておくとかなり便利ですよ!
音楽好き必見!AI音楽検索サービス「Maroofy」の魅力と使い方ガイド
音楽の趣味って人それぞれ違いますが、「この曲好き!でも似た感じの曲も知りたいな〜」って思うこと、ありませんか?
そんなときに使えるのが、AIを使った音楽検索サービス 「Maroofy(マルーフィー)」。
このサービス、なんとiTunesに登録されている1億2,000万曲の中から、自分が好きな曲と“似た雰囲気”の楽曲を探し出してくれるんです!
Maroofyってどんなサービス?
Maroofyは、AI技術を活用した音楽検索エンジンで、指定した楽曲をもとに「似てる曲リスト」をずらっと表示してくれる便利ツール。
音楽が好きな人にはたまらない「新しい出会い」を提供してくれるサービスです!
さらに、有料プランにすればApple Musicと連携して、自分のプレイリストに曲を保存できるという神仕様(しかもめちゃくちゃ便利)。
Maroofyの使い方は超カンタン!
使い方もいたってシンプル。パソコンでの使用を前提に設計されているので、スマホだとちょっと操作しづらいかも…という点だけご注意を!
基本の使い方は以下の通り:
-
Maroofyの公式サイトにアクセス
-
検索バーに好きな曲名やアーティスト名を入力
→ すると関連する楽曲の候補がズラッと出てきます -
その中から目的の曲を選択
→ 選んだ曲に似た雰囲気の曲が一覧で表示されます -
気になる曲の再生ボタンをポチッ
→ 試聴もできるので、サクッと確認できます!
操作もわかりやすく、検索履歴も残るので「前に探したあの曲…」ってときもすぐに辿れます。これは地味にありがたい!
実際に使ってみた感想
実際に何度か使ってみましたが…いや〜想像以上に当たる!
似ている曲がちゃんとピックアップされてて、「あ、これも好きな感じ!」ってなることが多かったです。
さらに:
-
普段は出会わないタイプの曲と出会える
-
似た雰囲気の曲がすぐに見つかるので、プレイリストづくりもはかどる
-
手作業で探してたころに比べて、めちゃくちゃ時短!
まさに音楽探しの革命。AIすごすぎる。
特に、iTunesに登録されていればインディーズ系の曲でもちゃんと認識してくれる点も好印象。
ちょっと気になるポイントも…
とはいえ、完全無欠ってわけではなく…。
Maroofyは似た曲を大量に出してくれるのですが、そのぶんジャンルが混ざってしまうこともあります。
「ロック系だけ探したい!」とか「R&Bの中で似た曲を知りたい!」みたいな場合、ジャンル絞り込みができないのは少し不便かもしれません。
でもまあ、いろんなジャンルを横断して聴く人にとっては、むしろ新鮮で楽しいかも。